拝啓
今朝の雷雨はまさに天の底が割れたかのような勢いで雨風と雷が。
ちょっとした嵐のような雨は、
午後から晴れ間を見せたものの深夜になっても降り止みません。
さて、
屋久島を『癒しの島』と位置付けたり、
それに憧れて島を訪れる方も結構いらっしゃいます。
確かに森に入って苔むす静かな空間に身を置いたり、
里のお姉さん達から集落の話などを聞いている時には、
「癒し系」の側面も感じられます。
しかし、
島に暮らせば荒天でフェリーは欠航、
雲が低くて飛行機は着陸できず、
なんでと思うような時に停電し、
ガソリンはサービスデーでも1リットル160円。
月に一度では済まない庭の雑草刈りに、
梅雨時のシロアリ(流し虫)やヤスデの来襲。
早ければ梅雨入り前から、
遅ければ11月過ぎまでご来島の台風。
自然の力強さ逞しさを前にして、
ヒトというものの存在の小ささ弱さを実感させてくれるのが離島のよさかもしれません。
人工物と商品にあふれた街にいると、
なんでも人間の力(金の力)でやりくり付けられるものだと錯覚して傲慢になり、
弱いものを軽蔑したり排除したりしがちですものね。
そんな屋久島には何故だか、それとも必然なのか、
いろんな分野の『アーティスト』や『職人』が移り住み、
様々な作品を産み出しています。
その一人、いえ二人が洋画家の高田裕子さん(http://www.yukotakada-work.com/profile/)とジュエリー作家の中村圭さん(http://kei-jewellery.com/)ご夫妻。
平内で「しずくギャラリー」(http://shizukugallery.com/)を開いていらっしゃいます。
高田さんの絵は洋画に興味のない方でも、

その高田さんが今月、
「水の森」という名の絵本を出版されたことをフェイスブックで今日知りました。
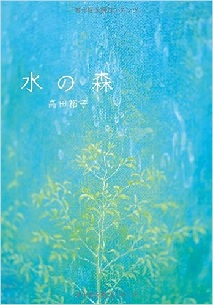
早速amazonで注文。
9月26日の「島の朗読会」までには六角堂明冥文庫に到着予定です。
バシャリドンドンと雷鳴とどろく豪雨の最中、
この絵本「水の森」を知ったことは天の啓示かと思わずにはいられませんでした。
これまで何となくぼんやりとは見えていたものの
これだとつかみきれなかったものの輪郭がはっきりしたのです。
「屋久島再活性化」の新たな切り口。
その切り口のキーワードが「みずのしま」、
いやいやもっと丁寧に
「おみずのしま」です。
海から湧きたつ水蒸気が島の斜面を駆け昇り、
雲となって雨を降らせ、
森の木々や苔を潤しながら沢を下って海に帰り、
森で蓄えた養分で海をさらに豊かにする。
そんなダイナミックな循環を劇的に体感させてくれるのが屋久島。

(落差88mの大川=おおこの滝)
それと同様に海を渡ってやってくる種々雑多な人々が
島の森や川や海を巡りつつ島に暮らす人々を潤して、
精気を蓄えてへ帰っていく。
ダイナミックな人の循環をイメージした、
といえば綺麗過ぎますね。
大人が「おみず」と言えば
「ホステス・料理店などの水商売のこと、また水商売に従事している人(とくにキャバクラなどのホステス)のこと」(ニコニコ大百科)。
つまりは、
人に喜びを与える「おもてなし」をすることで自分も喜びを得るという、
なんとも麗しい人間関係であり経営形態です。
と言うことは「島に歓楽街を作れと言うことか!」と思うのは安直。
「島に風俗をまき散らすつもりか!」と憤るのは早計。
皆既日食の年をピークに減り続ける観光客に
「今年の夏は暇だ暇だ」と毎年嘆き、
いつまでも「縄文様頼り」ではいけないと思いつつ
次の一手が見えないまま、
焦りばかりをつのらせて愚痴る前に、
まずはじんわりと
「おみずのしま」という言葉からにじみ出るイメージを
想い起していただきたい。

与えることと頂くこと、
それは本来同義。
さて、
ここでご提案する屋久島活性化「おみずのしまプロジェクト」とは……
次回乞うご期待。
敬具